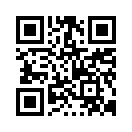サルボウガイはフネガイ科のアカガイの仲間です。現生種の学名は「Scapharca subcrenata(Lischke)」。大日層ではアカガイの仲間は多産し、その中には数種類があり、見分けるには、放射肋の本数で分類するのが容易で良いと思います。因みに「サルボウガイ」は放射肋が32本前後、「アカガイ」は42本ほどの本数です。サルボウガイは水深約10m前後の砂泥底のに棲んでいます。殻全体は厚く強度もあり採集自体は比較的容易でな貝ですが、殻に欠落がない完全な化石を探したり、完全な形であっても取り出し段階で破損をすることもしばしばです。特に後背縁の部分が欠けることが多く、欠けた場合は、接着材で補修します。殻が厚いため比較的良く接着します。また、食用として知られており、赤貝の缶詰はこのサルボウガイが使われているそうです。殻長が約の5cm~6cmほどとアカガイよりもだいぶ小さい貝です。ちなみに赤貝は10㎝をこえるものも珍しくありません。別名「モガイ」ともいわれ、サルボウという名前は漢字で「猿頬」と書き、猿が食べ物を口に含んで頬を膨らませた状態に似た膨らみのある貝ということです。
スズキ化石資料館見学ご希望の方は次のところまでご一報ください。
TEL 0538-42-4767 (鈴木まで)
 › スズキ化石資料館 › 掛川層群の化石 サルボウガイ
› スズキ化石資料館 › 掛川層群の化石 サルボウガイ › スズキ化石資料館 › 掛川層群の化石 サルボウガイ
› スズキ化石資料館 › 掛川層群の化石 サルボウガイ